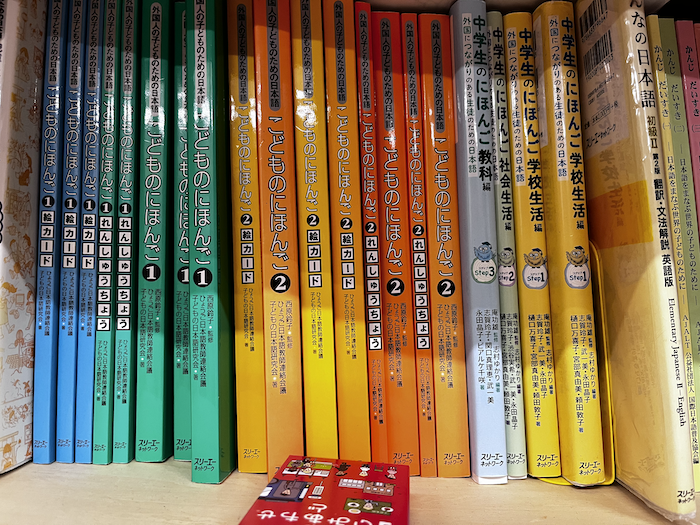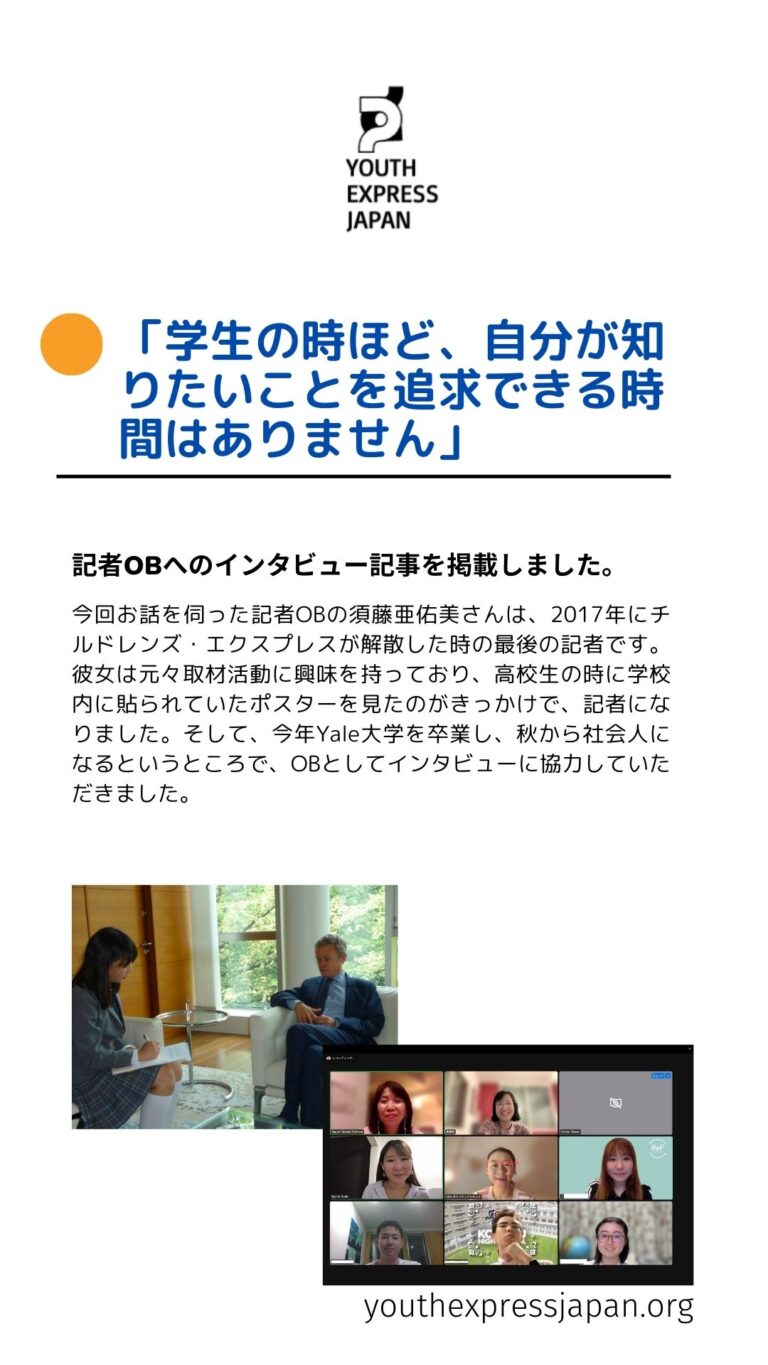「社会をよりよくしたい」という意思
記者:Nili Fukumoto(15歳)
2025年3月26日から27日にかけて、神奈川県横浜市の「上郷・森の家」で開催されたU18サミットに参加した。今年度のテーマは「FRESH」。全国から集まった中高生たちが、年齢や立場ではなく、これまで自分がやってきた活動や内に秘めた信念を軸に、対等に語り合い、共に考え、新たな視点を交わし合う2日間を過ごした。そこでは「社会をよりよくしたい」という意思が、人と人とを強く結びつけていた。
参加者は皆それぞれ異なる課題意識を持っていた。地方移住や教育格差、ジェンダーと政治、災害と福祉、似たような課題意識に見えてもそのバックグラウンドは違ったり、内容が難解なものが多かったが、それでも私たちは、限られた時間のなかで、互いの問いに真剣に向き合い、言葉を尽くした。
年齢や立場に関係なく、やってきたことの中身や問いの深さでつながるという経験は、これまでの学校生活の中では得られなかったものだった。むしろ、一般的な受験制度では、こうした問いを立てること自体が評価の対象にならないことも多い。だがこのサミットでは、どれだけ問いを立て、どれだけ他者にぶつけられたかが、その人の価値として自然に評価されていた。
私が最も印象に残っているのは、ディベートだ。私の班では、「音楽と政治」という一見関係が希薄に見えるテーマに対して、参加者それぞれが異なる入口から考察を深めていた。 日本においては、音楽や演劇などの芸術分野と政治との距離は遠いままだ。アーティストが政治的発言をすれば「空気が悪くなる」「黙っていればいいのに」という声が上がることすらある。一方でアメリカの大統領選挙では、候補者の支持を明言するミュージシャンが数多く登場し、大規模なコンサートが開かれるなど、音楽が政治的意思表示の手段として自然に機能している。
そんな国際比較から議論を始め、「なぜ日本では音楽と政治が分断されているのか」「表現の自由と社会的影響のバランスをどうとるか」「私たちは音楽を通じて社会に何ができるのか」など、次々と論点が広がっていった。わずか1時間ほどの議論だったが、誰一人として「時間が足りた」と感じなかったはずだ。それほどに、全員が全力で思考をぶつけ合っていた。
私がこのサミットで最も価値を感じたのは、むしろ「休憩時間」だった。コンテンツとコンテンツの間や、食事中、就寝前など、プログラム外の時間にこそ、最も深く人と関われた。誰かの活動を知り、その奥にある信念を語り合い、自分の考えを見つめ直す。そんな時間が何度もあった。
また、講演会の中で登壇された東京大学教授・慶應義塾大学特任教授の鈴木寛先生の言葉も、今の私に深く響いた。特に「自分の歪みを自覚する」という言葉が強く印象に残っている。この「歪み」とは、単なる欠点や短所ではない。他人と違っていること自体を意味している。
たとえば、「周囲と話が合わない」「共通の関心がない」と感じるとき、その“違い”を否定的に捉えがちだが、鈴木先生はそれを「偏りとして自覚し、それを意識した上で社会とどう関わるかを考えることが重要なのだ」と語られていた。
その言葉を聞きながら、私はこのサミットに来るまでの自分を思い返していた。日常の中では、自分の中の違和感をうまく言語化できず、流されるように過ごしてしまうことも多かった。しかし、ここでは「違和感を抱いている自分」こそが歓迎され、むしろその視点にこそ意味があるとされている。そして、それがまさに「自分の偏りを自覚し、語る」ことだったのではないかと思う。
2日間という短い時間の中で、私は何人もの「また会いたい」と思える仲間と出会った。私が語った問いに真剣に耳を傾けてくれた人、自分の信念を言葉にしてくれた人、沈黙の中でもそばにいてくれた人。そのすべてとの出会いが、自分の内側にある熱をまた少し高めてくれたように思う。
社会をよりよくする、という言葉は、簡単に使えば空虚なスローガンになってしまう。でも、誰かと語り、ぶつかり合い、考え抜くという営みを経たその先で生まれた言葉には、確かに重みがあった。
私はこれからも問い続けたいと思う。そして、その問いの輪を、また誰かと共有できる場所を探し続けたいと思う。

https://u18summit2025.studio.site/
記者雑感: サミットの運営を私たちと同じ高校生(過去のサミットの参加者)が行っている点も魅力的でした!少しでも同世代の高校生と交流してみたい方は是非来年のサミットに参加してみてください。