前提を疑う大切さと議論の文化について学ぶ
記者:尾崎惺 Satoru Ozaki (17)
「ディベート」と聞くと、海外特有の文化だと思う人も多いだろう。実は、私(記者)自身もそう考えていた一人だ。しかし、留学先のアメリカでディベートを経験する中で、その重要性を実感し、日本でももっと知ってほしいと考えた。帰国後、日本ディベート協会事務局長・専務理事であり、立教大学・異文化コミュニケーション学部教授の師岡淳也氏に取材をさせていただいた。日本におけるディベートの歴史やそのメリット、そして「議論の文化」が日本で根付くには、どんな意識が大切なのか、様々な視点から師岡氏の考えを伺った。
ディベートに馴染みのない日本
「ディベート」という言葉にあまり馴染みがない人も多いだろう。例えばアメリカと比べて日本ではディベートが盛んではない。それは日本の教育現場において、議論をすることが避けられてきたのが一因だろうと師岡教授は言う。
「政治的に中立であれ、ということが重んじられ学校で政治的な論争を避け、切り離すことが推奨されていました。例えば社会問題とか政治問題などに関して自分の意見を言う機会が学校現場では限られています。学校で政治的な議論が避けられてきた理由は様々ですが、その一つは60年代の学生運動*での生徒の過激な政治活動が問題視されたからだと考えられています」(師岡教授)。
*学生運動: 1960年代の日米安保闘争を機に、戦後の政治や社会に対する不満を背景に各大学で学生がキャンパスなどを占領するなどし、政府や大学当局への抗議を行った。
そのほかにも師岡先生は、現代のSNSなどが議論することが日本で避けられる要因を作っていると指摘する。
「SNSで政治的な発言をした人に対して非常に強いバッシング、中傷をすることが多く見られます。そうしたら、よほどの覚悟や信念がない限り、そこまでのリスクを冒してまで政治的な発言をしようとは思わなくなります。特にバッシングや中傷は若者や女性に向けられることが多く、その結果として、ますます若者が意見をいうのを忌避してしまうようになります。」
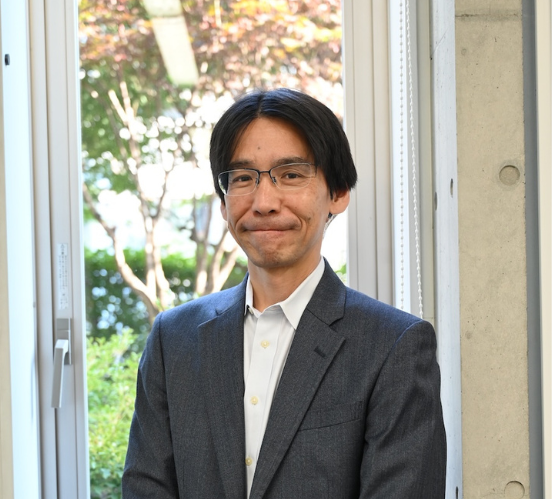
ディベートをするメリット?
ディベートをすることがなぜ私たちにとって重要なのか伺ってみた。
「誰かとは異なる意見を人前で述べる、ということに対して、ディベートを通して自分の中の許容性がより高まると思います。ディベートの場においては相手と意見が対立していることが前提ですし、相手の意見やそれを支える根拠に注意深く耳を傾ける必要があります。そうでないと、適切な反論はできませんから。そのため、ディベートを通して、議論をする相手への尊敬とまでは言いませんが、尊重する心が養える。これがディベートをする大きなメリットだと思います」(師岡教授)。
「ディベート甲子園」など一部イベントも盛んになってきたが、日本ではディベートの部活やサークルへの参加はいわゆる偏差値の高い学校、大学に通う人が多いのが現状だと感じる。師岡教授はディベートを「一部の人ではなく、幅広い層に実践して欲しい」と言う。ディベートを普及促進させるため、日本ディベート協会では年齢などの参加資格を設けない大会やセミナーを開催しているそうだ。
英語教育としてのディベート:日本の特殊性
さて、ディベート教育は国や地域によっても差がある。特にディベートの歴史が長いアメリカと日本では大きく異なる。例えば、参加人数である。アメリカには、ディベートのフォーマットがいくつかあり、リンカーン・ダグラス・ディベート*のように一対一などのディベートスタイルもあるが、日本は二人〜四人のグループがほとんどだ。「日本では大会の数が限られているので、より多くの高校生が参加しやすいように配慮した結果なのかもしれません」と師岡教授は指摘する。
一方、アメリカでは大学でもディベートが盛んであるのに対して、日本では大学生になるとディベート大会への参加者は減ってしまうそうだ。その原因として「ディベートを英語で行っている」ことが挙げられるという。師岡教授によると、アメリカではディベートが広く民主主義を支える重要なスキルとして認識されているのに対して、日本では歴史的にディベートは英語学習の手段という側面が強かったということだった。
*リンカーン・ダグラス・ディベート(Lincoln-Douglas Debate Format): アメリカで広く行われている一対一のディベート形式の一つ。その名称は、1858年にエイブラハム・リンカーンとスティーブン・ダグラスが行った連邦上院議員候補討論に由来している。
文化論が持つ強制力
インタビューで印象的だったのは「ローコンテクストか、ハイコンテクストカルチャーか」についての議論だ。私は米国留学前、日米のコミュニケーションの違いがこの言葉でよく説明されるのを耳にしていた。師岡教授は次のように語る。
「言語社会学者の寺沢拓敬さん*が言っているように、日本がハイコンテクスト文化で、アメリカがローコンテクスト文化という比較文化論は、常識のように受け入れられているが、学術的に立証されたものではないんです。また、日本人やアメリカ人がハイコンテクストかどうかを研究したものも、『程度の差』に過ぎず、統計的な有意差があるだけです。日本人にも主張を厭わない人がいれば、アメリカ人にも議論を好まない人がいます。集団間というよりも、集団内の個々の違いの方が大きいのです。」
*「日本人はハイ・コンテクスト文化、○○人はロー・コンテクスト文化」論にまつわる誤解(Yahooニュース)、言語社会学者・関西学院大学社会学部准教授 寺沢拓敬氏
師岡教授が懸念するのは、「こうした比較文化論が、文化的な規範として強制力を持つこと」だそうだ。
「ハイコンテクスト・ローコンテクストとか、日本は集団主義、アメリカ・イギリスは個人主義という文化論は、日本は集団主義的で出る杭は打たれる一方で、アメリカやイギリスは個人主義で自分のいうことが望ましいという考えに陥りがちです。それがさらに極端になると、日本の文化にはディベートは馴染まない、といった主張にもつながってしまいます」(師岡教授)。
異文化コミュニケーション
私が取材活動として興味があるテーマは「移民、多様性、インクルージョン」などだ。今回の取材で「ディベートを通じて自分の中の許容性が高まる(師岡教授)」という言葉を聞いて、日本にもっとディベートが広まれば、許容性のある人が増えて異文化コミュニケーションがもっと盛んになると感じた。師岡教授に異文化コミュニケーション促進についても伺った。
「一つは、中高生のうちから異文化交流の機会を増やすことです。留学に限らず、今はZoomを使えば交流は可能ですし、日本にも外国にルーツをもつ子供達が増えているので、一緒に日本語を使って活動をしたり、日本の文化について話したりする一方で、子供達のご両親の国の母語や文化を尊重するような異文化コミュニケーションが有効かなと思います。二つ目は、文化と国家を同一視しないこと。異文化を国対国のコミュニケーションだ、と狭くとらえるのではなく、文化的な背景が違う人同士のコミュニケーションだと定義を広げることです。例えば健常者と障害者、世代が違う人同士の対話も状況によっては異文化コミュニケーションと考えることができます」(師岡教授)。
「議論の文化」
最後に師岡教授より、次の言葉をいただいた。
「ディベート文化というと年がら年中議論しているみたいなイメージを持ってしまう人もいると思います。ですが、議論をしたくない人もいるわけで、それは尊重されるべきだし、その人たちが議論をしないことで何か不利益を被ったりするのは違うと思うんです。普段は議論しなくてもその人の考えとか立場を尊重するべきで、議論が必要な状況、例えば憲法の改正、移民の受け入れ、学校の校則など、そのコミュニティーに生きる人たち全員に影響を与えることに関しては、声がでかい人や一部の権力をもつ人の意見が強制されることなく、議論をして決めていくことが大事。それがたぶん僕の考える『議論の文化』なんですよね」(師岡教授)。
取材後記: 師岡教授には今回のテーマで参考になる記事をいくつか紹介いただいた。そのうち「日本の若者の「政治ぎらい」と〈政治教育〉の深い関係」早稲田大学 近藤孝弘教授(現代ビジネス、2019.12.22付)は、民主主義は自然に生まれるものではなく、政治的教育によって生まれるものであるという考えのもとドイツを例にあげ、政治教育の重要さを述べている。民主主義の問題点が次々と明らかになり議論の必要性が増す今、手段としてのディベートを日本で広めることは大変意義のあることだろうと感じた。
また、私を含め、海外の経験を積むほど「日本では」や「アメリカでは」など主語が大きくなってしまうことがよくある。しかし、本当の異文化コミュニケーションとは、相手を国別ではなく、より具体的な個別の背景や文脈に基づいてとらえる必要があるということをこの取材で学んだ。ディベートは”バトル”のように捉えられることが多いが、これからは”コミュニケーション”の一種として捉えようと思った。このようなきっかけを作ってくださった師岡教授に改めて感謝致します。







