小児がん研究・中川原章医師に聞く
記者:Yua Sato(17歳)
テレビで「横浜こどもホスピス」を知ったことが、小児がんに関心を持つようになった最初の出来事だった。私自身も病気を経験し、医療従事者たちとの関わりを通して、子どもたちを支える医療の現場を身近に感じてきた。小児がん患者と家族を支援する「ゴールドリボン」の活動を含め、小児がんについての社会での認知はまだ十分ではない。NPO法人小児がん・まごころ機構の理事長であり、医師の中川原章氏に取材した。この記事が、小児がんをめぐる状況を知るきっかけになれば幸いだ。
記者:日本ではピンクリボンなどが有名ですが、小児がんを支援する「ゴールドリボン」の認知度がまだ低いのはなぜでしょうか。
中川原先生:小児がんというのは、とにかく患者さんの数が非常に少ないのです。大人のがんに比べると圧倒的に少なく、数が少ないこと自体は良い面もありますが、認知度という点ではどうしても埋もれてしまいがちです。実際、日本では年間およそ100万人ががんになりますが、その中で小児がんは約0.3%、つまり1,000人に3人ほどにすぎません。それでも全国では年間2,500〜3,000人の子どもが治療を必要としており、決して小さな数ではありません。さらに世界では年間およそ42万人の子どもががんになっているという現実があります。したがって、私たちは日本の小児がんだけではなく、世界の小児がんにも目を向けて、一緒に取り組んでいかなければならないと考えています。
記者:以前、先生は「医療に不平等があってはならない」とお話しされていました。現在、国や地域によって生じている医療格差をどう捉えていらっしゃいますか。
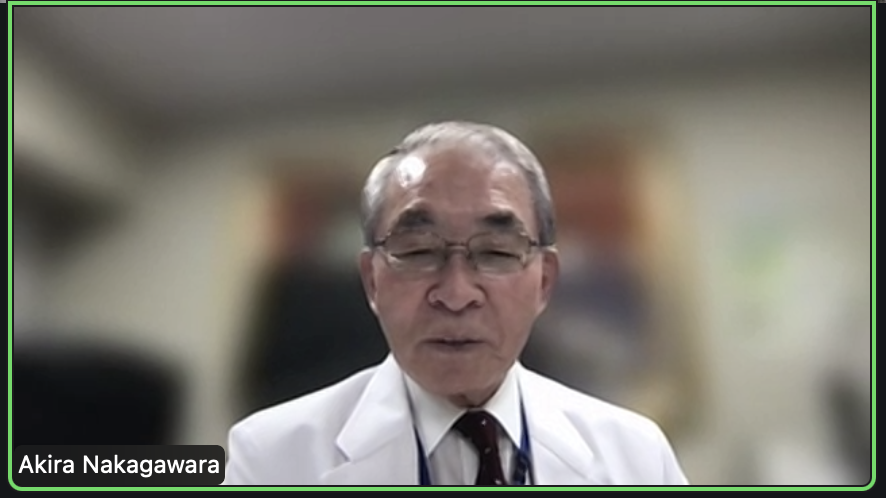
中川原先生:今おっしゃったことは非常に大事なポイントです。私たちの運動も、まさにそこに焦点を当てています。
日本にいて日本だけを見ていると分かりにくいのですが、日本も50年以上前はとても大変な状況でした。私が医学部を卒業した頃は、小児がんというのは「もう助からない」と言われていたんです。それで、私たちは小児がんを何とかしないといけないという思いで頑張ってきました。
ただ、日本の場合は、戦後の復興期、高度成長期を経て、経済的に大きく発展してきました。その流れの中で、日本ではだんだんと小児がんの子どもたちが助かるようになってきて、現在では欧米の先進国と同じくらいの治癒率になっています。小児がんの子どもたちの8割以上は助かる時代になりました。
もちろん、助かった後にも後遺症や晩期合併症といった問題はありますが、まず「命が助かる」ということは非常に大事で、その割合が8割を超えているわけです。
ところが今、世界レベル、あるいはアジアでもそうですが、所得の低い国、いわゆる貧しい国では、医療体制が十分に整っておらず、必要な薬もなかなか手に入らないなど、さまざまな理由で多くの小児がんの子どもたちがまだ助からず、そのまま亡くなってしまっている現状があります。
先進国では8割以上助かるのに、発展途上国では0%から多くても3割程度しか助からない。これは、「同じ地球上に同じ時代に生まれても、生まれた場所が違うだけで、先進国なら助かり、途上国だと助からない」という、全くの不平等です。
そこで今、国際小児がん学会とWHOが連携して、国連にこの問題を提起しました。国連では2018年に全会一致で採択され、これをグローバルな、みんなが共通して取り組むべき重大なテーマとして掲げ、「この格差をなくそう」という運動が今起こっています。私たちも、その流れの中でNPOとして活動しているところです。
記者:ありがとうございます。続いて、先生が小児がんの研究を志したきっかけを教えてください。
中川原先生:そうですね。まず、私の家は医者の家系ではありません。
きっかけの一つが、私の弟が2歳の時に急性灰白髄炎(ポリオ)にかかったことです。その治療の中でストレプトマイシンという薬を使ったんですが、それは結核にはよく効く薬で、当時は「ポリオにも効くのではないか」と期待されて使われた。しかし、その結果として弟は耳が聞こえなくなり、一生涯、ろう者として生きていかなければならなくなりました。これは私が幼い頃の大きな出来事でした。
もう一つは、私の父が、私が小学校5年生の時に胃がんで死んだことです。そのことで家庭も大変な状況になりました。この二つの出来事が大きな理由です。
特に父親ががんで亡くなったことで、「どうしても敵を討たなければならない」と思うようになりました。
記者:先生が研究の道に進まれた1970年代当時、小児がんの医療現場はどのような状況だったのでしょうか。
中川原先生:私は「がんの研究をしたい、がんの治療をする医者になりたい」と考えて、学生時代から自分なりにいろいろ勉強していました。しかし、その頃は、がんというものがまだほとんど分かっていなかった時代で、勉強してもなかなか答えが得られませんでした。がんの研究といっても、何をテーマにして良いかさえ分からず、ずっと模索していました。
卒業前の臨床講義で、いろいろな科の先生方の講義があったのですが、その中で、外科の助教だった池田圭一先生(のちに私の恩師になる方)が、インキュベーターに入った赤ちゃんを講義室に連れてこられたことがありました。
その赤ちゃんは人工呼吸管理を受けていて、管を気道に入れて呼吸を調整しながら生きている状態でした。お腹がパンパンに張っていて、「この赤ちゃんは生まれてまだ1か月だけれど、お腹の中はほとんど全部がん細胞なんだ」と先生は説明されました。
さらに、「この赤ちゃんは助かるんだよ」と言われたんです。今はお腹の中も血液の中もがんでいっぱいだけれど、ある時から自然に治り始める、と。先生は同じようなケースをそれまでに2例経験されていて、この赤ちゃんは3例目だと。だから「この子は間違いなく助かる」とおっしゃった。
それを聞いたとき、私は本当に驚きました。全身にがんが広がっているのに助かる、そんながんがあるのかと。この、「自然に治るがん」のメカニズムを知りたいと思い、その講義を聞きながら「これを自分のライフワークにしよう」と決めました。これが小児がん研究に邁進する最初のきっかけでした。
卒業してすぐ池田先生の外科に入局し、「小児がんをやりたい」と申し出て、そこでトレーニングを受けながら、研究の道にも入っていきました。
当時は、がんの研究というのは「どこから手をつけていいか分からない」ような時代でした。大人のがんの細胞を培養して、細胞株を作ることができるようになりつつあって、「がん細胞の株を作るだけでも教授になれる」と言われるくらいの時代でした。でも、がん細胞の株を作ったとして、その先に何をどう研究すればいいのかという手がかりは、ほとんどありませんでした。
そこで私は、「若いうちに生化学をしっかり勉強しておこう。将来、本格的にがん研究ができる時代が来たときに備えて、自分の力をつけておこう」と考えました。がんそのものとは別のテーマで生化学の大学院に進みましたが、その経験がのちにロックフェラー大学への留学につながり、自分にとっては非常に良かったと思っています。
私が若い頃はそういう時代でしたが、その後の10年ほどで状況は大きく変わりました。「がんは遺伝子の病気である」ということが次々と分かってきたのです。これは私にとって非常に大きな刺激になりました。
臨床で小児がんの患者さんを治療しながら、遺伝子の勉強をし、「小児がんでは遺伝子がどうなっているのか」を研究するようになりました。約15年ほど臨床を続けたあと、40歳を過ぎてから二回目の留学をしました。この時は本格的に臨床を一旦やめ、「これからは遺伝子・ゲノムの時代になる」と考えて、アメリカに渡り、大学の学生たちと一緒に基礎研究をしながら、小児がんの遺伝子・ゲノムの研究に本格的に取り組み始めました。
記者:昔は今ほどがんは大人の死亡原因ではなく、結核や脳卒中などの別の病気が主な死因として挙げられていたと聞きました。
中川原先生:当時は今のように長生きできる時代ではなく、がんになる前に感染症で亡くなる人が多かったのです。特に戦後の時代は結核が非常に多く、結核で亡くなる人がたくさんいました。ですから、まず感染症が大きな問題として前に立ちはだかり、その段階で亡くなる方が多かった。
しかし今は、感染症は多くの薬や対策によってある程度コントロールできるようになり、人々が長生きするようになってきた。その結果、長生きすればするほど「がんになる確率」が急速に高くなるわけです。現在は、がんが圧倒的に多い時代になりました。
記者:二度の米国留学を経験されていますが、そこでの一番の学びや気づきは何でしたか。
中川原先生:本当にたくさんあります。人生というのは長いようで短い。その中で二回も留学できたというのは、私にとって非常にありがたいことだったと思っています。
一回目は、よく分からないまま留学したところがあります。がんの研究をしたかったのですが、ほとんどがんの研究はできませんでした。ロックフェラー大学では、ザンビル・コーン教授の研究室で免疫の勉強をしました。
その研究室には、後に樹状細胞(デンドリティックセル)を発見してノーベル賞を受賞するラルフ・スタインマンという助教授もいて、毎日同じ研究室で顔を合わせていました。彼が行っていた樹状細胞の研究も間近で見ていました。それが後にノーベル賞につながったわけです。
そういう環境の中で免疫学を学べたことは、研究者として非常に良い経験でしたし、「サイエンスとは何か」を教えてもらった場でもありました。
日本にいた頃は、「研究者になるには卒業してすぐ研究に進まなければいけない」「一度でも臨床を経験してから研究者になろうとする人は基本的にダメだ」といったことを言われる時代があり、私自身もそういうことを言われて悩んだことがあります。「本当にそんなルールがあるのか?」と疑問を持っていました。
ところがロックフェラー大学に行ってみると、全く違っていました。医学研究をしている人の多くが、いったん臨床を経験してから研究の道に進んでいたのです。ザンビル・コーン教授自身も、ハーバードで臨床をしてから研究に入り、世界的なトップリーダーになっていました。
そうした経験を通じて、「サイエンスとは何か」「研究者としてどう生きるか」ということを深く教わったのが、一回目の留学でした。
その頃は「がんと免疫は結びつかない」と言われていましたが、二回目の留学の頃には時代も変わり、私は小児がんの臨床と遺伝子の研究をある程度自分で進めたうえで、「小児がんの遺伝子・ゲノムの研究を本格的にやる」という目的を持ってアメリカに行きました。この頃は時代の流れも、自分の準備も、人との出会いも本当に恵まれていました。小児がんに特化して、素晴らしい経験ができたと感じています。アジアで小児がんの活動をするうえでも、ここで得た人脈や経験は非常に役に立ちました。

NPO法人 小児がん・まごころ機構
https://mocc4u.org/


-30-40分-768x768.png)



