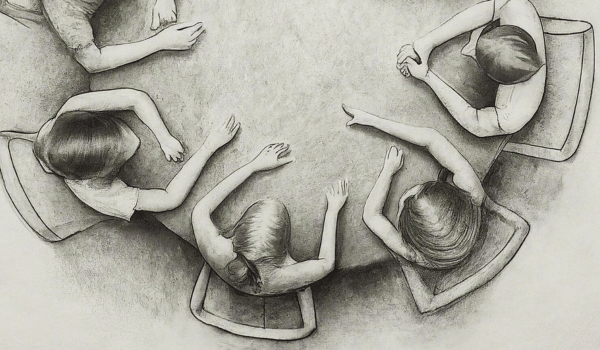編集者という仕事、志す若者へのメッセージ
記者:邊愛 Pyong Sarang (17)
前編に続き、後編では作品作りと編集者という仕事について、株式会社新潮社の文庫出版部・新潮文庫編集部編集長の大島有美子さんに詳しく語っていただきました。
作家と二人三脚で歩く編集者
今回の取材で、一つの本が出版される流れは、まず雑誌で連載されたものが単行本となり、その数年後に文庫化されると知りました。雑誌、単行本、文庫の編集者がそれぞれ連携し、一人の作家に三部署から担当が付くのが基本スタイルです。「本当に作家にはさまざまな個性の方がいて…それぞれに合わせてカスタマイズした対応をしていくことが編集者には求められます」と大島さんは教えてくれました。

プロット(あらすじを含む全体像や重要点をまとめたもの)の段階で、作家と編集者で「直木賞を狙おう」とか「大ヒットを狙おう」等と相談しながら、一緒に構成を練っていきます。原稿が上がってきたら、編集者は細かく鉛筆を入れ修正を繰り返していくのだそうです。「もちろん、編集者の手を借りず、一人で素晴らしい作品を書き上げる作家の方もたくさんいらっしゃいます。しかしたとえ相手がベテランの作家であっても、編集者は率直に意見を伝えて、作品をより良いものにするお手伝いをします」(大島さん)。
編集者としての苦労
新潮文庫の編集者には、通常はいくつかの部署を経験した人が多いそうですが、文庫編集部一筋でずっと働いていたという大島さんに編集者として印象に残ったエピソードを聞いてみました。
「私が担当した思い出深い作品の一つが、重松清さんの『くちぶえ番長』です。この作品は文庫オリジナルとして出版されたものでした。当時、私は20代の経験の浅い編集者で基本的な編集技術すら身についておらず、重松さんにはいろいろなご迷惑をおかけしました」と苦笑しながら大島さんは振り返ります。
「この作品はもともと小学館の『小学四年生』という雑誌で連載されていたもので、とても素敵な作品なのですが、『小学生に向けて書かれた物語が、文庫の読者に読んでもらえるだろうか』と不安もありました。ところが、今では30万部を超えるロングセラー。実は私の子どもが小学校で『くちぶえ番長』を読んだよ、と言っていて、当時の自分が知ったら驚くだろうな、と未熟だったころを恥ずかしくも懐かしく思い出しました」(大島さん)。
編集者として気を付けていることについても質問しました。
「言葉で何かを表現することは誰かを傷つけたり害したりする可能性があるということを、常に意識しなければならない、と思っています。作家には表現の自由を生かしてもらいたいですが、その言葉が世に出た時、どんな反応があるかに無意識でいてはいけません」(大島さん)。

出版業界を志す若者へ
取材の最後に、出版業界を志す若者へアドバイスをいただきました。
「本が好きでたくさん触れておいたほうがいい、というのは基本ですが、それに加えて、何か好きなことや得意なことがあればいいですね。特に新潮社はエンターテインメントだったり、ノンフィクションだったりと、さまざまなジャンルの本を刊行している出版社なので、自分の得意分野をたくさん持つことで、作家にアイデアを提供できる引き出しの多い編集者になれるのではないかと思います」(大島さん)。
取材後記: 私は、去年の12月から記者としていくつか取材を経験し、毎回頭を捻らせながら記事を書いています。学生時代は自分の「アイデアの倉庫」に、少しずつ好きなことや得意なことを蓄えていく。自分にしかできない唯一無二の個性を磨いていく大切さを今回の取材で学びました。
書店に新しい本を探しに行くと、いつの間にか新潮文庫のコーナーに足を運んでいるくらいに、私は新潮文庫が大好きです。今回取材させてもらえたこと、貴重なお話をたくさんお聞きできたこと、まるで夢のようで今も嬉しい気持ちでいっぱいです。大島さんをはじめ、取材にご協力いただいた皆様に心から感謝申し上げます。
自己紹介: マイペースな高校2年生です。取材も記事もまだまだ稚拙ですが、取材活動を通して少しずつ記者として、人として成長していきたいと思っています。