フィリップス・ジャパンの事例から考える
記者:Rion Kutsumizu (17歳)
ジェンダー平等は、今の日本社会に浸透しているように見える。SDGsの目標5*が掲げられ、企業では女性管理職比率が叫ばれている。政治の世界でも、「女性活躍」や「多様性」は頻繁に語られ、日本初の女性首相誕生も実現された。しかし、高校2年生の私は将来の進路を考える中で、「キャリア」と同時に「家庭」や「子育て」についても現実的に考えるようになった 。とりわけ家庭内の役割分担には依然として大きな格差があるのではないか。男性の育休取得は増えているようだが、表面的な前進の裏にある現実を知りたいと株式会社フィリップス・ジャパンに取材した。
*SDGsの目標5: 国連が定めた2030年までの国際目標(SDGs)のうちのひとつで「ジェンダー平等を実現しよう」というテーマのこと
今回の取材では、異なる立場から「男性育休」に向き合ったお二人に話を伺った。一人は、2023年に5ヶ月間の育休を取得した人事部の奥津元春さん。もう一人は、ビジネスマーケティングマネジャーIGTS部門の岩崎晃一さんだ。岩崎さんは、部下の育休取得を現場で見てきた。お二人は別部署だが、「取る側」と「穴を埋める側」それぞれの立場から話を伺った。
なぜ制度があっても男性育休は広がらないのか。背景には長時間労働を是とする風潮や、育児を女性の役割とする固定観念、ハラスメントへの不安、さらには復職後のキャリアへの懸念など、日本特有の課題があるのではないか。そこで今回は、比較的支援体制が整っていると思われる大手企業を取材した。制度の「使いやすさ」だけでなく、取得する側と送り出す側が直面するリアルな葛藤を明らかにすることが、本取材の目的である。
目次

「育休で抜けた人員の穴を埋める側」の岩崎晃一さん
育休取得の動機と現実
まず、育休を取ろうと思った一番の理由を教えてください 。
奥津さん:もともと子供ができたら一生懸命育児に参加したいという希望がありました 。また、夫婦とも両親が遠くに住んでいるので、自分たちで何とかしなければならないという切実な状況もありました 。
実際に取得してみて、いかがでしたか ?
奥津さん:子供の成長にずっと立ち会えたのは本当に良かったなと思います。できることが日に日に増えていって、食べるものも最初ミルクだったのが少しお乳も飲めるようになったり、ちょっとずつ離乳食が始まったりとか、 人間ってこんなに変わるんだっていうのをすごく実感しながら、有意義な時間を過ごせたかなと思います。ただ、大変さは想像以上でしたね 。24時間つきっきりで、自分でメリハリをコントロールできません。「立ち止まれない」という感覚は、今までの人生で初めての経験でした 。
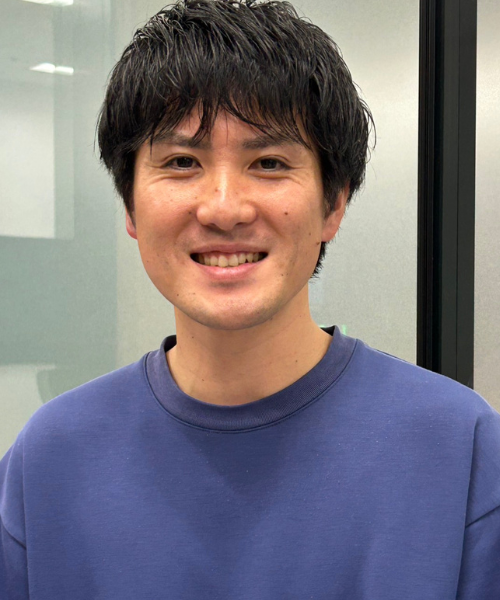
職場の反応とサポート
育休取得前の職場の反応はどうでしたか ?取得後はどんな感じでしたか?
奥津さん:取る前は「ぜひどうぞ」とウェルカムな感じでした 。私の上司もお子さんがいる方で理解いただけたのだと思います。復職した後ですが、それほど大きく困ったりはしなかったですね。それでいうと、女性は一般的に 1年以上取られる方がうちの会社の全体の傾向としては多いので、体力的なことも含めて色々と復職後は大変なことがあると思います。
周囲のサポート体制は整っていたのでしょうか 。
奥津さん:私の育休中、会社の人たちは、連絡をおそらく控えててくれたと思うので、育児に専念できたことは、職場の人にはすごく今も感謝しています。
以前、中小企業の方に取材した時、男性の育休は取りづらいとかサポートがなかったとか聞くことがあったんですが、やっぱり大手の会社は整ってるんでしょうか。
岩崎さん:「制度が整っているから育休が取りやすいしうまくいく」という解釈は少し違うかもしれません 。はっきり言って、何か特別な制度があるわけではないんです 。育休を取得した部下を持つ立場として言うならば、休む人本人より「残された人をどう支えるか」が一番大事です 。抜けてしまった部分をチームとしてどう支えるかが、上長の力量や課題になります 。
具体的に、残されたメンバーの負担はどのようにカバーするのですか ?
岩崎さん:私のチームでは従業員2人が同じ時期に育休に入り、20%の馬力がなくなりました 。誰かが抜けてもすぐに代わりが補充される実態はないし、残された人の給料が増えるわけでもありません 。だからこそ、メンバーに少しずつ負荷を割り振り、「みんなで支え合おう」というマインドを醸成していくしかありません 。
残されたメンバーから反感が出たりしませんか。
岩崎さん:育休を取得した部下を持ってる立場として言うならば、その彼らを支えるっていう、彼らを支えるというより、残った人をどう支えるか、ここが一番大事です。だからこそ、上司は常に残った人たちのケアをし続けなければなりません 。やっぱり増えてしまった労働量に対して大丈夫か、と気を配る。ここを疎かにすると、育休から戻ってきた人が気持ちよく復帰できなくなってしまいます 。

育休を取る側のスタンスと支える側
奥津さん: 実は私は最初はもっと長く育休を取る予定でしたが、休み中に会社に連絡した際、仕事が回っていないことが分かって短縮して復帰したんです 。育休を取って良かったのは間違いないですが、周りに迷惑をかけていたのも事実です 。組織全体のバランスを取らなければいけない上長の大変さっていうところまで私自身も考えが及んでいなかったし、やっぱり綺麗な面もあれば、実は泥臭い課題がありますよね。職場の人たちは、それぞれ思ってることが違うっていうのは事実としてあると思います。
岩崎さん:(育休を取る人を送り出す側からすると)育休を取る側のスタンスって、今の段階では重要ですね。「育休とります、さようなら」と丸投げするのではなく、自分の業務を整理して、「助けてください。お願いします」と、他のメンバーに「迷惑かけるけれども、休ませてください」と言えるスタンスの人であれば、みんなも「じゃあ、助けようかな」ってなりますよね。やっぱり、相互理解がものすごく大事。でも、そういう相互理解とかをしなくてもいいようにするためには、会社として制度を整える必要がある。それが給料なのか、評価なのか分かりませんが、制度を会社が敷くと、多分、相互理解とかそんなことはいちいち考えなくてもいいのかもしれないです。
未来を担う世代へのメッセージ
今後、男女問わず誰もが育休を取れる社会を作るために、まだ若い世代に伝えたいメッセージがあれば伺いたいです。育休制度のことは学校では教わらないことですが、普及していくべき大事なことではないかと思います。
岩崎さん: 社会の流れとして、「男女共の育児参加はやった方がいい」という風に、この10年で劇的に変わりました。ちなみに私、子供 3人いるんですけど、1回も育休取ってないんですね。これは後悔してます。「あなたあの時、育児参加してなかったじゃん」と言われるし、一生言われると思います。やっぱり取れるなら取った方が良かったと思います。今は男性も女性も仕事と育児が両立しやすいように社会を作り上げている最中で、皆さんが社会人になる頃には、もっとやりやすい環境になっていると信じています 。
奥津さん:アドバイスとして伝えたいことは2つあります 。1つは、「子供を持ちたい」という気持ちがあるなら、恥ずかしがらずに発信してほしいということです 。私自身、高校生の頃は「結婚」のイメージも湧かず、子供がほしいと言うことって恥ずかしいことだ、と思っていました 。でも、育児は大変ですが本当に楽しいです 。皆さんの世代から、そうした気持ちをオープンに語れるカルチャーを作ってほしいと思います。
もう1つは、「どうしても分かり合えない価値観がある」と知ることです。私の母は働いていましたが、共働きで母親が働いているだけで「子供が可哀想だ」と言われたそうです。20年、30年で社会は劇的に変わります。皆さんが社会に出る頃にも、まだ古い考えを持つ人は残っているでしょう 。でも、それを「古い」「間違っている」と切り捨てるのではなく、背景にある違いを認めた上で、自分たちのカルチャーを作ってほしいと思います 。

取材後記: 取材中、「社会の厳しさに絶望しないで」と冗談交じりに声をかけられた。しかし、今回の取材で私が感じたのは絶望ではなく、「まだ足りない」という現実だった。育休を取得した本人だけでなく、その間の業務をカバーする同僚や上司の負担、そこに生まれる不満や葛藤は、想像以上に重いものだった。一方で、株式会社フィリップス・ジャパンは、大手企業として制度が比較的整っており、育休を「取りやすくしよう」とする努力や姿勢も強く感じられた。そうした環境でさえ、なお壁が存在するという事実は重要だ。もしこんな大きな会社でさえ難しさが残るのだとすれば、例えば、制度や人員に余裕のない日本の中小企業では、より深刻な課題があることは想像に難くない。その結果として、育児に十分関われなかった男性が生まれ、父親と過ごす時間を持てない子どもが生まれ、キャリアを継続できなかった女性が生まれる。この問題は決して「男性育休」だけの話ではなく、家族全体、そして社会全体に連鎖的な影響を及ぼしている。だからこそ、この問題から目をそらすことはできない。制度を整えようとする動きがある一方で、なぜ取得率は伸び悩むのか。なぜ政治や政策の議論の中で、育休やジェンダーの問題が前面に出たり出なかったりするのか。選挙や世論との関係、企業の取り組みの限界、そして文化との結びつきについても、引き続き考えていきたい。
自己紹介: 次は、中小企業の現場や、政府がどのような課題認識を持ち、どのような改革を進めようとしているのかを取材したい。男性育休をめぐる問題は、制度・政治・文化が絡み合う構造的な課題であり、その解決には、現実を直視し続ける姿勢が不可欠だと感じた。






