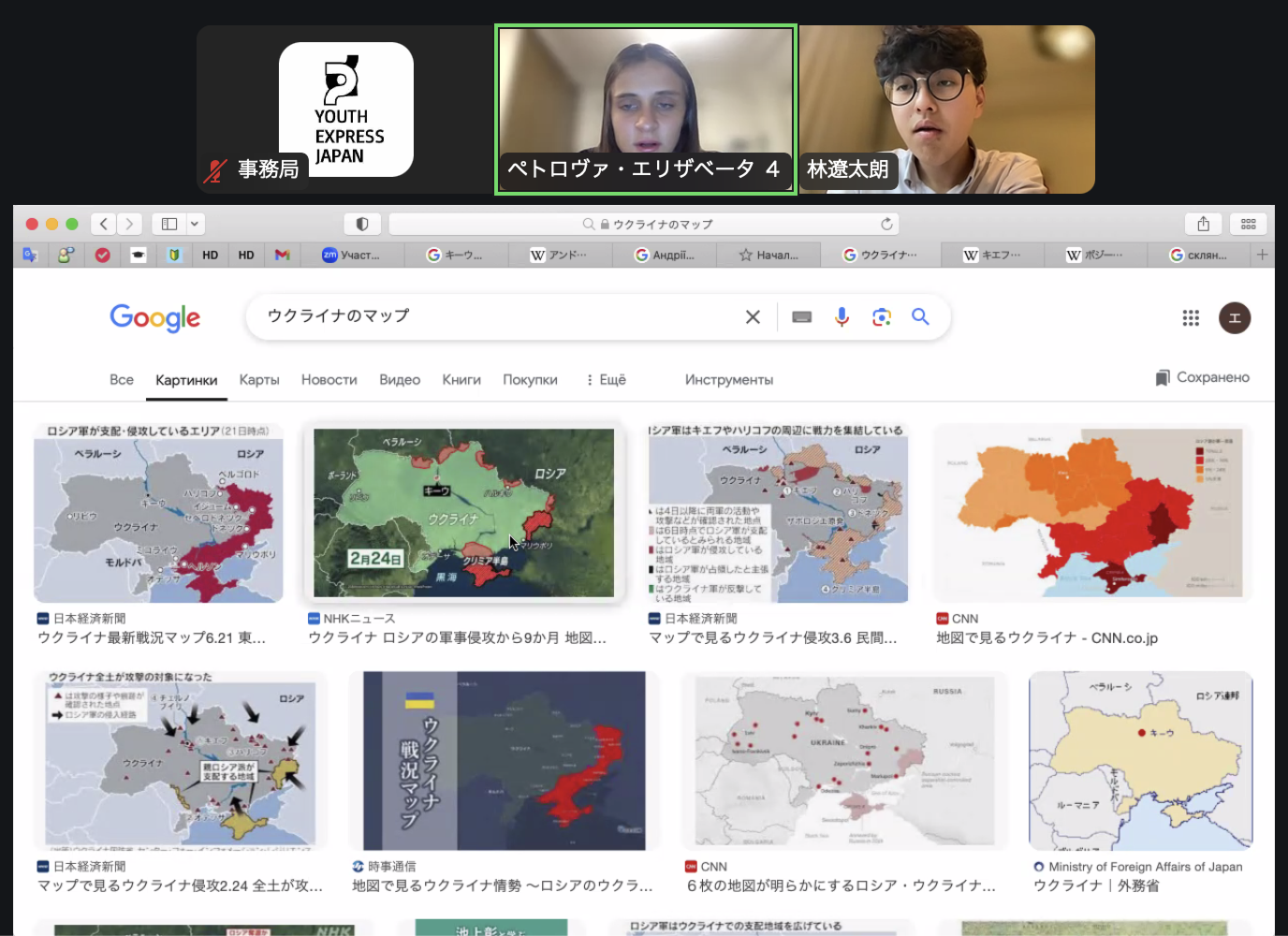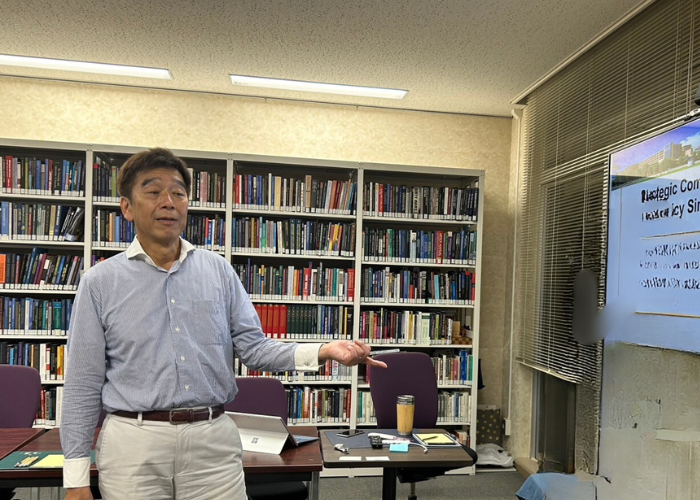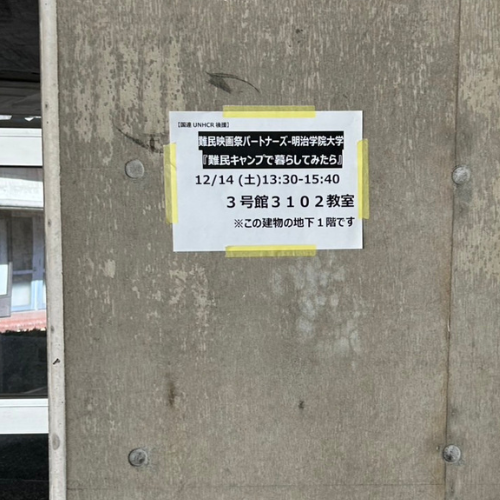エリザベータ・ペトロヴァさんにインタビュー
記者:林遼太朗 Ryotaro Hayashi (17歳)
2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、戦争や難民といった言葉を身近に聞く事が増えた。現在も戦闘は続いており、両国で多大な犠牲が生まれている。トランプ大統領の就任などにより、今後のウクライナ情勢にも変化が生まれると予想される中、実際にウクライナの人々は戦争をどのように捉え、今後を考えているのだろうか。侵攻直後の2022年3月にキーウから福岡県へ避難してきたエリザベータ・ペトロヴァさんにインタビューを行った。
生まれ育ったキーウ
ウクライナの首都キーウは、エリザベータさんが生まれ育った故郷の街だ。日本の高校生に向けてキーウを紹介するならどのような街かと尋ねると、様々な名所を教えてくれた。「私はキリスト教の教会やアンドレイ坂、ゴールデンゲート(黄金の門)といった場所が好きで、キーウにはこのような独特で美しいスポットが多いです」と、笑顔で語る。
しかし、侵攻が始まって以来、ウクライナでは教会をはじめとする歴史的建築物が破壊され、多くの文化財が危険にさらされている。私は将来、記者として戦争報道に関わりたいと考えているが、テレビでニュースを見ていると、戦争を伝えることの難しさを強く感じる。ただ戦況や被害の数字を報じるだけで十分なのだろうか。
戦争がもたらす被害は、人的なものにとどまらない。人々の心の拠り所となる風景や街並みが失われることで、深い傷が残ってしまうのだ。エリザベータさんの話を聞き、そのことを改めて実感した。

ウクライナの現状
2024年6月時点で、約2600人以上がウクライナから日本に避難民として来ている。エリザベータさんもそのうちの一人だ。キーウ国立言語大学で日本語を専攻しており、避難民として来日後に交換留学制度があった日本経済大学を卒業し、現在は日本の企業に勤めている。「日本の支援はとてもしっかりしていて、日経大では学費の支援や私を含めた70人のウクライナ人学生を受け入れてくれました」と流暢な日本語で話す。彼女は日本に一人で来てからはキーウにいる家族と毎日電話をしているそうだ。
ウクライナの現状について「8月にキーウに帰った時に破壊された建物を見てショックを受けました。私の知り合いが亡くなる事もあり、現地では戦争が始まってから街の警報は止まず、毎日3、4回はサイレンが鳴ってミサイル攻撃を受けています」と語る。侵攻から約3年が経過した現在でも、ウクライナでは身近で人が亡くなり、建物は壊され、国民が大きく傷ついている現状がある。さらに「これからのウクライナは戦争終結が優先事項で、電気やエネルギーなどのインフラの復旧が必要です」と現状の課題点を話す。
また、エリザベータさんはロシアによるクリミア侵攻が起こった2014年の時を回想する。「当時はウクライナが政治的に弱まっていて、その時から侵攻が始まりました。キーウでも人が亡くなりましたが、当時私は子供で殆ど危機感は感じませんでした。でも、次第に侵攻がはじまったことによるショックは大きくなりました。」
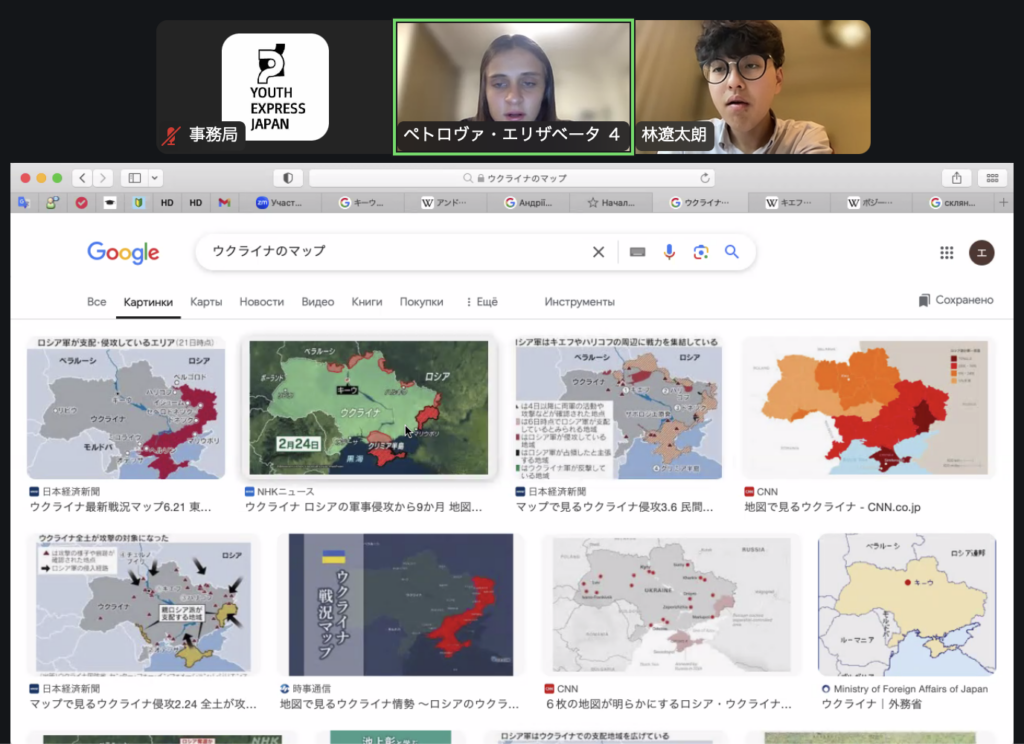
戦争においてメディアが果たす役割
私はエリザベータさんへの取材から、戦争報道がどの様に国際社会に影響を与えるのだろうか、と疑問に思った。そこで彼女に戦争被害者であるという立場で、ウクライナでの外国のマスメディアが果たす役割を聞いた。
「マスメディアの役割は非常に大切です。報道を通じて、私たちウクライナ人の声や国際支援の必要性を様々な国の人に伝え、理解をしてもらい、皆が戦争終結に向けて行動することが必要です。またウクライナは武器の供給を欧米諸国から受けていますが、これも海外のメディアによる報道の影響が大きいです」と話す。
侵攻から約3年が経った現在、侵攻直後と比べてウクライナ情勢がTVや新聞などで取り上げられる機会が減っている。しかし、この戦争により生活や命を奪われ、国を追われる人々が世界には存在する。エリザベータさんへの取材から、引き続き戦争の現実を伝え、私たちはより問題意識を持つ必要があると強く感じた。
エリザベータさんと日本
エリザベータさんはキーウ国立言語大学で日本語を専攻し、日本語検定一級を取得している。彼女がなぜ日本語を熱心に学ぶのか、理由を聞いた。「私は小さい頃に『千と千尋の神隠し』を見て、劇中に出てくる日本文化に興味を持ちました。ウクライナでは特に若者が日本のアニメに強く関心を持っています。私もそのうちの一人で、大学で日本の言語や文化を学びたいと強く思いました」と目を細めた。アニメなどの日本文化が遠く離れた国でも人々に夢を与え愛されていることを知り、私はとても驚いた。
そんな日本に対し、ウクライナ人はどんな印象を持っているだろうか。
「ウクライナ国内では日本はアジアの中で一番ウクライナを支援している国として知られ、日本に対する気持ちは強いです。これからも日本とウクライナの関係はより大きく重要になっていきます。」と前向きな姿勢を示した。

日本のこれからの若者に伝えたいこと
最後に、戦争当事者としてエリザベータさんが日本の若者に伝えたいことを聞いた。
「第一に戦争を当たり前にしてはいけません。戦争前、ウクライナでは政治的汚職が広がっていました。それが『力』による侵攻を招いた一因でもあります。日本の若者には『自分の国を大切にする』という思いを持ってほしいです。何か問題が起こってから政治家に判断や考えを委ねるだけでなく、自分ごとと捉えられるとよいです」と彼女は締め括った。
私たち自身が国の未来を考え、行動する必要性。今回の取材では戦争の悲惨さを知る人からのみ得られる、平和への独自の視点を感じた。
2025/2/20
タイトルを「ウクライナ難民に聞く、平和への道」から「ウクライナ避難民に聞く、平和への道」に修正しました。
日本政府は、ウクライナからの避難者を「避難民」として受け入れており、「難民」ではなく特別な人道的措置で対応しており、これは、日本が加盟する難民条約(1951年の「難民の地位に関する条約」)に基づく「難民」とは異なる扱いのため。また出入国在留管理庁は公式発表において「避難民」という表現を使用しているためです。
参考資料: 出入国在留管理庁「ウクライナからの避難民の受入れについて」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001372940.pdf
取材後記: 約1時間の取材の中で、エリザベータさんからは終始、母国を愛する想いと日本への感謝が感じられた。また私たちも日本文化をより理解し、継承に務める必要があると強く思う。実際に「戦争からの避難民の声を聞く」という貴重な取材から得た学びを通じて、今後も戦争報道を通じて現状をよりよくする探究を続けていきたい。
自己紹介: 最近、毎日のように何処かに赴いて記者活動をしています。実際に現地へ足を運ぶとその街のイメージや活気がわかります。横須賀に行った時は潮風が冬でも心地よく感じ、心落ち着く場所なのだなと感じました。今後も様々な場所を訪れて自分の感性を磨き、取材活動を楽しみたいです。